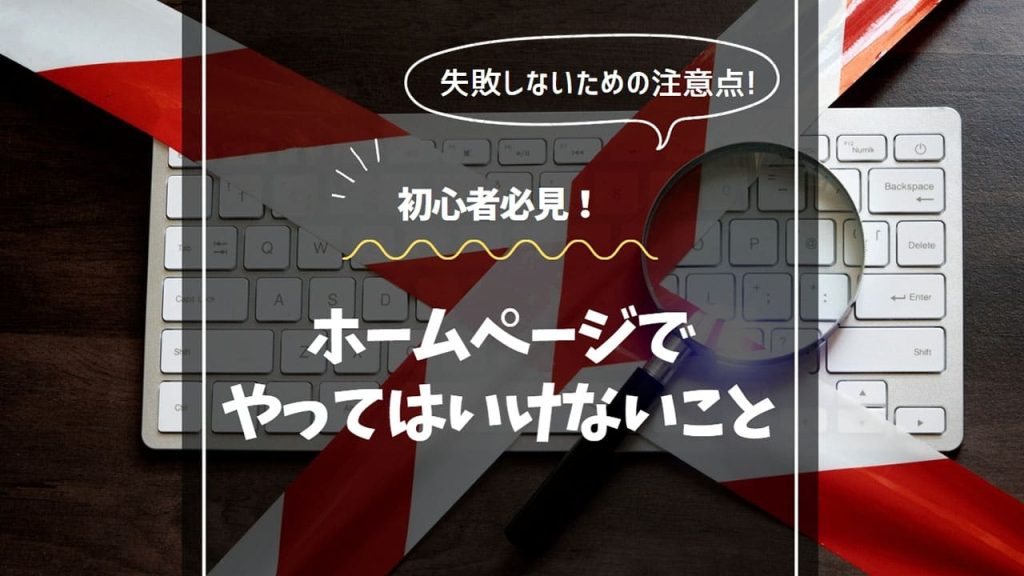
ホームページでやってはいけないこと25選!失敗しないための注意点を解説
ホームページを作成する際、ただデザインや機能にこだわるだけでは成功には繋がりません。企画・設計段階での目的やターゲットの明確化、数値目標の設定、サイト構築時のセキュリティやユーザビリティの重視、さらにデザインやコンテンツ作成の一貫性が重要です。
もちろん、ホームページを作成して終わりではありません。運用・保守を定期的に行い、より良いホームページへと成長させていきましょう。
本記事では、ホームページ制作においてやってはいけないことを徹底解説します。ホームページで失敗しないためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
企画・設計段階でやってはいけないこと

ホームページを作成する前の企画・設計段階でやってはいけないことは2つあります。
目的とターゲットが曖昧
ホームページを作成する目的と、ターゲットが曖昧だと、ホームページ自体のコンセプトが定まりません。なんとなくホームページを作成したとしても、誰に充てたものかわからず、せっかく訪問してくれたユーザーもすぐに離脱することでしょう。
| ホームページの種類 | 作成する目的 |
|---|---|
| LP | 商品・サービスを購入してもらう |
| コーポレートサイト | 企業のことを知ってもらう |
| 採用サイト | 人材を採用する |
| オウンドメディア | SEOによって商品・サービスを認知してもらう |
| ECサイト | 商品を直接販売する |
| プロモーションサイト | キャンペーン情報を発信する |
上記の大まかな目的を元に、もう少し具体的に落とし込み、それに沿ったターゲットを設定してください。
数値目標を設定していない
KPI(中間目標)、CV(最終目標)は明確に設定しておくべきです。認知度向上・検索結果上昇・会員登録増加などの目的に対して、どんな機能が必要で、いつまでにどのくらいの数字を達成させるかのスケジュールが明確になります。
具体的な数字で目標設定をしておかないと、思うように利益が上がらない、どこを改善すべきかわからないなどのリスクが生じてしまいます。
サイト構築時にやってはいけないこと

主にWebコーダーやディレクター向けですが、サイト構築時にやってはいけないことを4つ紹介します。
不適切なサーバーとドメインの選択
無料サーバーや無料ドメイン・共同ドメインなど、不適切なものを設定するのは避けましょう。個人ブログであれば良いですが、企業用ホームページだとセキュリティや容量などの問題が出てきます。
セキュリティがしっかりした有料サーバーを選ぶ、ドメインは企業名やサービス名など認知度向上に繋がりそうなオリジナルのものを使用するなどしてください。
セキュリティ対策を怠る
ホームページを作成する上で、セキュリティ対策は必須と言えます。情報漏洩や、不正アクセス、第三者によるホームページ改ざんなど、悪用されるリスクを防ぐからです。
もし企業が上記のようなトラブルに見舞われると、ニュースや新聞で報道され信用度もガタ落ちになる可能性もあります。
サイト構造とナビゲーションの不備
ホームページの全体構造となる「サイトマップ」の作成、ページ単体の構造である「ワイヤーフレーム」を作成し、サイト構造全体に不備がないか確認しましょう。サイト構造に不備があると、たどり着きたい情報が見つかりにくくなります。検索エンジンからの評価も下がるので、丁寧に作成しましょう。
もちろん、ホームページにアクセスしたユーザーがどのページにいるのか確認するための「パンくずリスト」も、ナビゲーションに当たります。
SSL化していない
SSL化とは、ホームページの通信を暗号化するものです。「https:」のように「s」がついているものがSSL化されたホームページです。セキュリティの1種ではありますが、Googleが推奨しているのでSEO対策を行うホームページであれば必須と言っても過言ではないでしょう。
SEOでの評価がされやすい、第三者によるデータの改ざんやなりすましを防げるなどのメリットがあります。
デザイン関係でやってはいけないこと

ホームページのデザインに関しても、やってはいけないことがあります。ここでは4つの注意点を解説します。
トンマナを決めていない
トンマナは「トーン&マナー」のことで、デザインや文言などに一貫性を持たせることを意味します。デザインにおいて、トンマナを決めておかないと、ページごとに全く別のホームページになってしまう可能性があります。
ユーザーも、別のホームページに移動したと混乱してしまい、離脱してしまいます。せっかくホームページを作ったとしても、ユーザーが離れて行ってしまうので本末転倒になるでしょう。
デザインコンセプトが不明確
デザインを作成するときは、コンセプトを明確にしてください。士業系ならお堅いイメージ、アパレルなら清楚やポップなどブランドに合わせたコンセプトにするなどです。
ターゲットとコンセプトがずれてしまうと、ユーザーに刺さりません。むしろ、見ていて疲れるホームページと認識されるかもしれません。ユーザーを獲得するうえで、コンセプトを明確にすることは重要なので必ず決めておきましょう。
ユーザビリティを無視する
ユーザビリティは、ユーザーにとっての使いやすさを意味します。ページ表示速度が軽い、導線がわかりやすく操作性が良い、どこになんのコンテンツがあるか明確などです。ユーザーにとってストレスのないホームページを意識して作成しましょう。
モバイルフレンドリー不対応
モバイルフレンドリーは、スマートフォンに最適化したホームページのことを指します。検索エンジンとして主流のGoogleが、PCサイトのGooglebotクロールを停止してモバイルサイトで評価すると発表しています。今ホームページを作成するなら、スマートフォン対応は当たり前と言って良いでしょう。
初めからモバイルサイトを作成する、PCとスマートフォンの両方に対応したレスポンシブデザインにするなどで、モバイルフレンドリー対応してください。
コンテンツ作成時にやってはいけないこと
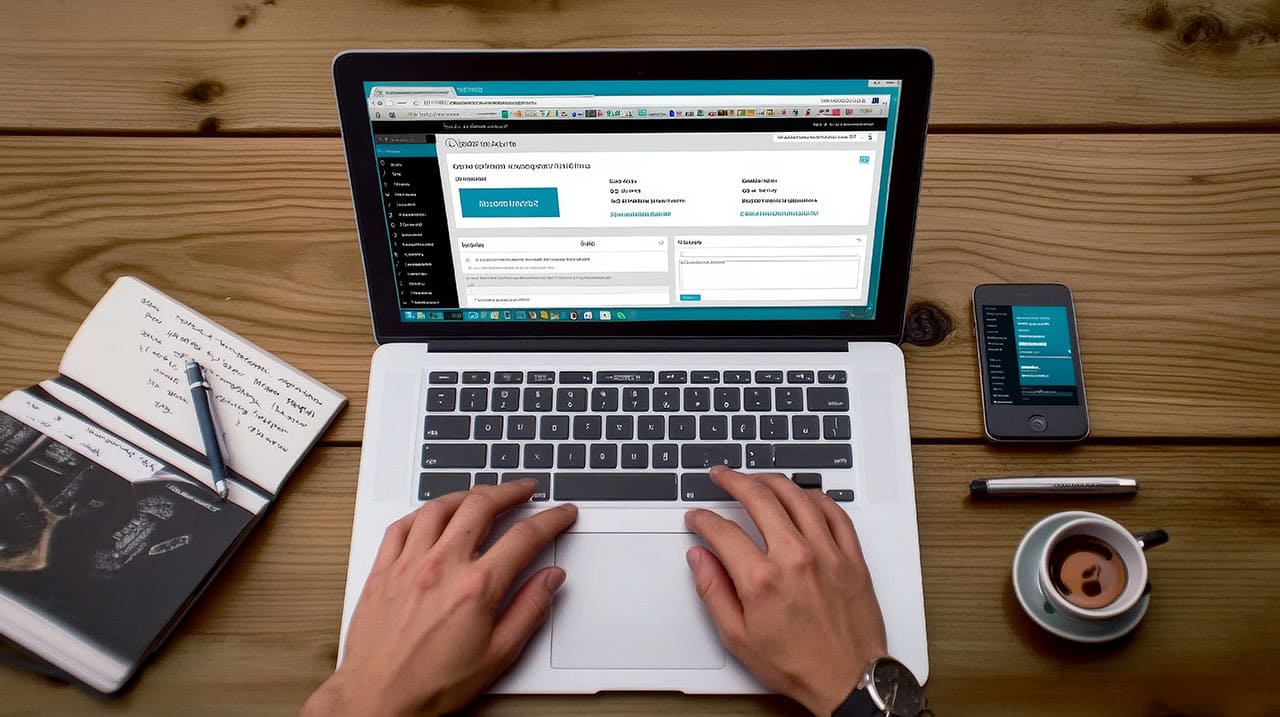
ホームページに掲載する情報、コンテンツ作成時に特にやってはいけないことを4つ紹介します。中には権利違反になり、最悪の場合は企業間での裁判に発展することもあるので、ホームページを作成する際には必ず覚えておきましょう。
コンテンツの無断転載
コンテンツの無断転載は厳禁です。許可なく第三者が複製した場合には、著作権侵害になってしまうからです。民事・刑事の両方で裁判になるリスクがあります。企業としての社会的信用度が落ちてしまうので、絶対にやめましょう。
どうしても、コンテンツの内容を用いりたいときは「引用(著作者の明記)」という形で利用してください。
著作権の無視
すでに作成されている文章や画像・写真などのあらゆるコンテンツには著作権が存在します。先述した無断転載だけではなく、無断で修正を加える、トレースして類似のものを作成するなども、著作権の侵害とみなされます。
とくにフリー素材を使用するときは「商用利用可」のものを使い、利用や加工をしても大丈夫なのかを確認しておきましょう。
質の低いコンテンツの提供
質の低いコンテンツは、SEO評価をもらえないだけに関わらず、サイトの評価を下げる原因にもなります。情報量が少ない・内容が薄い、重複コンテンツやコピーコンテンツなどは作成しないようにしておきましょう。
また、コンテンツの自動生成や、隠しテキストもNGです。スパムと認識されるリスクがあります。
画像や動画のサイズが大きすぎる
画像や動画のサイズが大きいコンテンツは、ページだけでなくホームページ全体を重くする原因になります。SEO評価が悪くなるだけではなく、ユーザーがホームページに来てくれないなどのデメリットが生じます。
なお、Googleによると、ページが表示されるまでに3秒かかると直帰率は32%増加、5秒だと90%とほとんどの人が離脱すると言われています。
SEO対策においてやってはいけないこと

数あるやってはいけないことの中から、コンテンツSEOに関してとくにやってはいけないことを4つ紹介します。
不適切なリンクの獲得・購入
被リンクは、外部のWebサイトから自社のWebサイトまたはページへ向けられたリンクのことで、外部SEOに最も効果があると言われています。ですが、業者からリンクを購入したり、低評価のサイトから大量にリンクを貼るなどの行為は、スパムとみなされてペナルティを受けるリスクがあります。
被リンクを獲得する際は、数よりリンクしてくれたサイトの質を優先しましょう。
キーワードの過剰使用
SEO対策において、検索キーワードを入れてコンテンツを作成することは有効です。ですが、キーワードを過剰使用してしまうと、本来対策したいキーワードが埋もれてしまう、関係ないキーワードで順位が上がって逆効果になる恐れがあります。
メインキーワードと、それに付随した関係性があるキーワード2~3ほどの対策に抑えておきましょう。検索結果が異なるキーワードであれば、別コンテンツを作成して内部リンクを貼るなどで強化するのも良いです。
重複コンテンツの作成
重複コンテンツは、その名の通りコンテンツの中身がほかのものと重複している状態です。検索エンジンからの評価や被リンク評価が分散される、共食いを意味するカニバリゼーションが起こるなどのデメリットがあります。
SEO的にも悪影響なので、コンテンツの量を増やすなら内容が同じになっていないかを確認しておきましょう。なお、外部サイトのコンテンツと類似な、コピーコンテンツもSEO評価が下がる原因となります。
画像のalt設定をしない
altは、画像の代替えテキストです。画像が表示されない時にどんなものなのかを解説したり、盲目の人用の読み上げツールで画像の解説をする際に役立ちます。
検索エンジンのBot 「クローラー」は、テキスト情報しか認識できないのでaltは重要となります。クローラー向けに画像にどんな情報が入っているのか示す役割もあるからです。SEOを意識するならキーワードを盛り込むのもありですが、基本的にはコンテンツに沿った代替えテキストを入力しましょう。
運用・保守に関してやってはいけないこと

ホームページ作成後の運用・保守でもやってはいけないことがあります。ここでは4つのやってはいけないことを紹介していきます。
定期的な更新とメンテナンスを怠る
定期的な更新やメンテナンスは、コンテンツの質を保つだけではなく、ユーザーにきちんと運営しているということを示すのにも有効です。
更新がされていないホームページだと、廃業・倒産したと思われやすいです。情報が古く、見ても価値がないと認識されるので離脱率も高くなるでしょう。
セキュリティ対策を継続しない
SSLやファイヤーウォールなどのセキュリティを継続しない場合、不正アクセス・情報漏洩・第三者によるホームページの改ざんなどのリスクが高まります。企業としての社会的信用度を失うことにも繋がりかねないので、セキュリティ対策は継続して行うべきです。
CMSのアップデートを怠る
CMSを使用しているホームページの場合は、CMSのバージョンのアップデートも怠らないようにしましょう。古いバージョンはサポートされていないのでセキュリティが弱くなります。脆弱性を放置することになるので、不正アクセス・情報漏洩・第三者によるホームページの改ざんなどのリスクが生じます。
運用マニュアルを作成しない
企業でホームページを運営する場合、異動や退職などで担当が変更することは良くあります。運用マニュアルを作成していない場合、後任のスタッフが更新できない、触ってはいけない箇所を修正したなどのトラブルに見舞われる可能性があります。
簡単なものでも良いので運用マニュアルを作成し、やり方を伝達したほうが良いです。もしできるなら、知識がない人でも運用できるような具体的なマニュアルを作りましょう。
外注時にやってはいけないこと

ホームページ制作を外注する時にやってはいけないことも紹介します。外注先によっては、ホームページの完成度にも関わるので選定は特に慎重に行ったほうが良いです。
業者選定の誤り
ホームページ制作会社の中には、まれに悪質な業者も存在します。実績が少ない、費用が割高、ネット上での評判が悪いなど、少しでも不安に思う要素がある場合は、その業者は避けましょう。
万が一悪質な業者に当たった場合は、ホームページの出来が悪い、欲しい機能が備わっていない、内部SEO対策がされていない、コードが汚いなどのトラブルに見舞われる可能性があります。
契約内容の不確認
外注にホームページ制作を依頼するときは、必ず契約内容を確認してください。「作業範囲」「保証」「途中解約の有無」「コンテンツやサーバーの所有権」「保守範囲」など、見逃してはいけない内容ばかりが記載されています。
とくに、ホームページの所有権については必ず譲渡されるのかは見ておくべきです。見逃してしまうと、完成したホームページの所有権が外注のままで、コンテンツの更新やリニューアルなどが行えないといった事態に見舞われます。
ホームページ制作を外注に丸投げ
ホームページ制作を外注に丸投げしてはいけない理由は、依頼者の意図が反映されないリスクがあるからです。外注先に完全に任せてしまうと、企業のブランドやターゲットに合ったデザインができないことがあります。
例えば、テンプレートを使い回してしまうと個性が出ず、ありきたりなデザインになってしまいます。そのため外注先と連携して、定期的にチェックやフィードバックを行うことが大切です。丸投げせず、関わりながら進めることで、理想に近いホームページとなるでしょう。
まとめ

ホームページ制作は、単なる見た目や機能だけでなく、戦略的な視点を持って進めることが重要です。企画段階では目的とターゲットをしっかりと定め、サイトが達成すべき数値目標を明確にすることが成功の鍵となります。構築時には、セキュリティやユーザビリティを考慮し、コンテンツやデザインが一貫性を持ち、ターゲットに響くように設計しまましょう。運用・保守段階では、定期的な更新やセキュリティ対策を欠かさず行い、サイトの信頼性を保つことが大切です。
さらに、外注を利用する場合には、業者選定を慎重に行い、契約内容や進行状況をしっかりと確認しながら進めることが求められます。外注先と密に連携し、ブランドに合ったデザインや機能が反映されるようにし、完成度を高めることが求められます。これらのポイントを守ることで、長期的に効果的なWebサイト運営が可能となり、ユーザーに信頼されるホームページを作り上げることができるでしょう。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
ARTICLE
2022/03/02( 更新)
Instagram(インスタグラム)のプロアカウントとは?切り替え方法・やめる(解除)方法などもあわせて解説
SNSInstagram
-
ARTICLE
2024/02/26( 更新)
お弁当屋・仕出し屋の集客方法14選!人気店になるためのコツを徹底解説
企業経営業種別
- 飲食店
- 集客
-
ARTICLE
2023/04/17( 更新)
整体院はホームページで差がつく!制作時のポイントと参考デザインまとめ
企業経営業種別
- 整体院
-
ARTICLE
2024/06/03( 更新)
飲食店の開業に向けた流れを解説!成功に繋がる準備のポイントと資金の目安
企業経営業種別
- 飲食店
