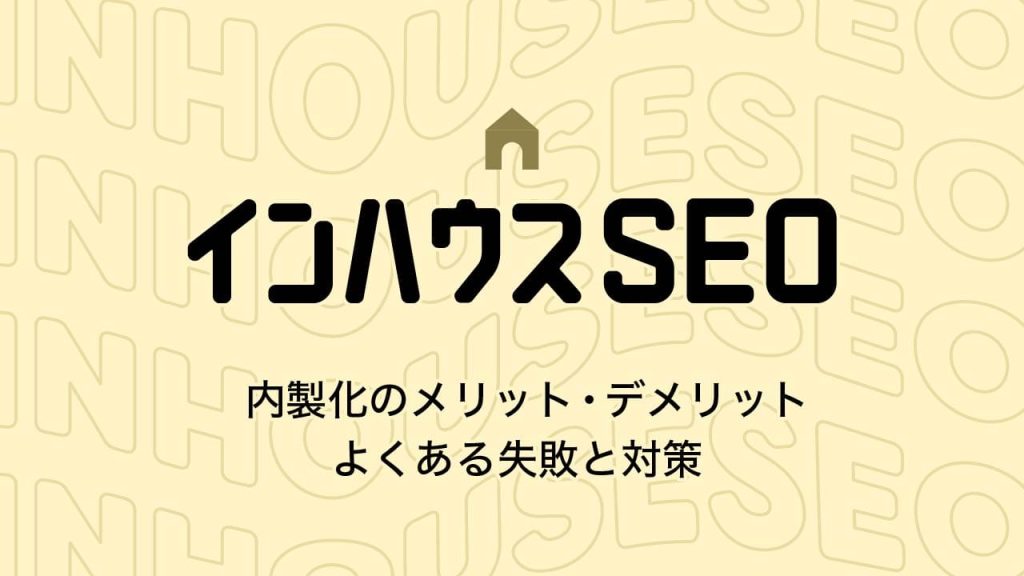
インハウスSEOとは?内製化するメリット・デメリットやよくある失敗と対策
近年ではSEOを内製化するインハウスSEOに取り組む企業が増えています。集客やブランディングにおいてSEOは重要な施策であり、外部ではなく社内で取り組むことで多くのメリットを得られます。
しかし、そもそもインハウスSEOのメリットやデメリット、円滑な移行の方法など、よくわからないという方も多いでしょう。
本記事では、そもそもインハウスとは何か、向いている企業や導入する際のポイントを解説します。インハウスSEOの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
インハウスSEOとは

インハウスSEOとは、企業が自社内でSEO対策を行うことです。専門の知識や経験をもつスタッフが中心になり、社内で施策の立案・実行、分析、改善に取り組みながらWebサイトやコンテンツの上位表示を目指します。
近年、インハウスSEOを導入する企業が増加傾向にあります。SEOに関する情報が以前に比べて入手しやすくなったことや、コンテンツマーケティングなどの包括的なマーケティング手法が広まったことで、自社内で完結した方が成果を向上させやすくなったことがあげられます。
しかし、専門知識を持つ人材の育成や確保、変化の激しいSEOの継続的なキャッチアップ、社内におけるSEOへの理解促進など、課題も少なくありません。
それでも、課題を一つひとつクリアし、自社でデータを分析・実践しながらノウハウを蓄積することで、持続的な成長につなげている企業が増えています。
インハウスSEOのメリット

インハウスSEOに取り組む企業が増えているのは、それだけのメリットがあるからです。特に注目したいのが以下の5項目です。
- 運用のコスト削減につながる
- ノウハウや知見を社内にためられる
- PDCAサイクルを早められる
- 他部門と連携したマーケティングに取り組める
- 新たな事業アイデアのタネになる
それぞれくわしく解説するので、インハウスSEOの導入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
運用のコスト削減につながる
インハウスSEOの一つ目のメリットは、運用コストの削減につながることです。外部のSEO会社にSEO対策を委託する場合、月額費用や成果報酬などが発生します。データの分析レポートや対策の立案だけで高額なコストが発生することも少なくありません。
一方、インハウスSEOは社員の人件費は発生するものの、外部の委託費用に比べて大幅に削減できます。コンテンツ作成を自社で行うことで記事作成の代行費用を抑えられ、費用対効果の向上が期待できます。
ノウハウや知見を社内にためられる
SEOに関するノウハウや知見が社内に蓄積されることも、インハウスSEOのメリットです。外部委託の場合、取り組みの内容や結果について報告を受けるのみのケースが多く、ノウハウはたまりにくい傾向にあります。
そもそも、なぜその取り組みを実施したのかよくわかっていない、ということも少なくないでしょう。担当者が理解できていなければ、社内や決済者が理解するのはより難しくなります。
その点、インハウスSEOなら取り組みの過程で実践的な知識や経験が社内に蓄積されます。
時には成果がでないこともありますが、取り組む過程で得られた失敗体験も、重要な情報です。特に、効果がでなかった原因を分析しながらGoogleのアルゴリズムを理解することで、施策の成功率を高められます。
SEO対策においてアルゴリズムの理解は必須事項のため、実際に分析や施策に取り組みながら知見を貯めることは、自社内の大きな財産となります。
PDCAサイクルを早められる
PDCAサイクルを迅速に回せることも大きなメリットです。SEOは変化が激しく、取り組んだ結果、すぐに成果を出すこともあります。インハウスSEOなら、成果が出たらすぐに次の行動に移せるため、よりスピード感を持って改善に取り組めるでしょう。
ただし、順位が下がった時に慌てて対応するのは悪手の場合もあります。コアアップデートで一時的に下がったとして、また元に戻るケースは少なくありません。そのため、改善が必要なのか待つべきなのかを判断することは重要です。
それでも、変化の激しいSEO環境において、迅速な対応は競争優位性を保つ上で重要です。
他部門と連携したマーケティングに取り組める
インハウスSEOなら、他部門と連携したマーケティングも推進しやすくなります。外部委託の場合は共有できる情報が限られ、社内全体での連携が不足する傾向があります。
一方、インハウスSEOはSEO担当者が社内にいるため、広報部や営業部など、他の部門と連携しやすくなります。広報部が発信するニュースリリースに合わせてSEO対策を行ったり、営業部からの顧客ニーズの情報に基づいてコンテンツを作成することで、より効果的な集客につなげたりすることが期待できます。
このように、部門間の連携を強化することで、マーケティング全体の効果を最大化できます。
新たな事業アイデアのタネになる
インハウスSEOで得られたデータや知見は、新たな事業アイデアにつながる可能性を秘めています。SEO対策を行う過程では、ユーザーの検索行動やニーズに関するデータなどを幅広く収集できます。
どのようなニーズが多いのかが分かれば、そのニーズに応える新しい商品やサービスを開発するヒントになるでしょう。競合サイトの分析を通じて、市場の動向や潜在的なニーズを発見できることもあります。
SEO活動を通じて得られた情報は、Webサイトの集客だけでなく、事業戦略全体に貢献する可能性を秘めています。
インハウスSEOのデメリットや課題

インハウスSEOは、コストの削減やノウハウの蓄積、新たな事業アイデアの創出など様々なメリットがありますが、デメリットも存在します。特に注意したいのが以下の三点です。
- ライターや編集者を採用するのが難しい
- チームが成熟するまで費用対効果が悪化しやすい
- 最新情報やトレンドを知る機会が減る
事前に理解していれば適切な対策をとることも可能です。それぞれ、解説します。
ライターや編集者を採用するのが難しい
インハウスSEOは、分析や施策の立案だけではなくコンテンツの制作も自社内で行いますが、質の高いライターや編集者を確保するのは簡単ではありません。
クラウドソーシングの登場でWebライティングを副業にする方は増えましたが、経験や知識が浅いことが多く、企業運営のコンテンツとして公開するには質がたりていないことが少なくありません。
もちろん高い専門知識や文章力をもつライターはいますが、需要が高く、採用競争が激しいのが現状です。報酬が高くなりやすく、他案件も抱えているため製作数が少なくなる可能性もあります。
このように、質の高いライターを確保することは、インハウスSEOにおける大きな課題の一つと言えます。
チームが成熟するまで費用対効果が悪化しやすい
インハウスSEOチームが立ち上げ初期段階では、費用対効果が悪化しやすい傾向があります。適切な分析や対策ができず、キーワード選定のミスやコンテンツの低品質化により検索順位が上がらないケースがあります。
SEOやアルゴリズムや知識が少ない場合、安易にブラックハットなどの楽な手法に取り組んでしまい、結果的にペナルティを受けてしまう、という可能性もあります。
ノウハウや知識が貯まるのはメリットですが、実務に活かせるまでは時間が必要になることが多いのは理解しておく必要があります。
最新情報やトレンドを知る機会が減る
最新情報やトレンドを知る機会が減ることも、インハウスSEOの大きな課題です。SEO会社は様々なクライアントのSEO対策を行っているため、その分だけケーススタディに取り組めます。また、業界のセミナーやイベントなどに参加する機会も多く、最新の動向を把握しやすい環境にあります。
一方、インハウスSEOでは、情報源が自社のデータや限られた情報源に限られるため、少ないサンプルからSEO環境を把握しなければいけません。他社が発信しているブログやSNSから情報を得る方法はありますが、具体的なデータはないため、明確な裏付けを取りにくいという側面もあります。
SEOにおいて最新の情報を得るのは欠かせないため、情報収集の手段を確保しておくことが重要です。
インハウスSEOが向いている企業の特徴

インハウスSEOはメリットもデメリットもあるため、本当に自社で取り組めるのか、不安に思っている方もいるでしょう。そこで、インハウスSEOが特に向いている企業の特徴を3つの視点から解説します。
- 経営層がSEOの重要性や傾向を理解している
- SEOの専門スキルを持った専任者がいる
- 長期的な視点で予算や時間を確保できる
全てを備えている必要がありませんが、当てはまる項目が多いほど、インハウスSEOの成功に近づくでしょう。各要素を確認しながら、自社は向いているのか検討してみてください。
経営層がSEOの重要性や傾向を理解している
インハウスSEOを成功させるためには、経営層の理解と協力が欠かせません。SEOは中長期的な施策であり、プロジェクトへの投資に対して、回収までの時間は長くなる傾向にあります。
また、Googleのアルゴリズム変動などでSEO環境は常に変化しており、コアアップデートにより、一時的に大きく順位を落としてしまうこともあります。
もし経営層のSEOに対する理解が不十分な場合、順位やトラフィックが落ちたことだけを見てSEOの取り組みを軽視してしまう場合があります。しかし、十分な理解があればリソース配分や他部署との連携が可能になり、継続的な成果に繋げることができるでしょう。
経営層のSEOへの理解は、インハウスSEOを成功に導くための重要な要素となるのです。
SEOの専門スキルを持った専任者がいる
社内にSEOの専門知識を持った専任者がいることも、インハウスSEOが向いている企業の特徴の一つです。
SEOは、ウェブサイトの構造やコンテンツ制作、技術的な取り組みなど、関わる要素が多岐に渡ります。そのため、それぞれの知識やスキルを一から教育して身につけるためには、時間やコストが発生します。
しかし、すでにSEOの専門スキルを持った専任者がいれば、短い期間で適切な施策に取り組むことができ、そして成果を生み出せるでしょう。また、専任としてアサインすることで、変化が激しいSEOトレンドを適切にキャッチアップして、より高度なSEO戦略を立案・実行することも可能です。
もし社内にSEOの専門スキルを持った専任者がいるのであれば、インハウスSEOを検討する価値は十分にあると言えます。
長期的な視点で予算や時間を確保できる
長期的な視点で予算や時間を確保できることも、インハウスSEOで成功しやすい企業の特徴です。
SEOは、コンテンツ作成やサイト改善など、地道な作業の積み重ねが重要です。しかし、短期的な成果を求めすぎると施策が中途半端になり、十分な効果を得られない可能性があります。ペナルティのリスクがあるブラックハットSEOに着手してしまう場合もあるでしょう。
その点、長期的な視点があれば、コンテンツ作成に十分な時間を確保してユーザーニーズにあった高品質なコンテンツを制作しやすくなります。また、中長期的な取り組みを行うことで、コアアップデートの影響を受けにくい本当に質の高いWebサイトを構築できるようになります。
長期的な目標に向かって粘り強く取り組める体制をもつことが、インハウスSEOを成功に導くための土台となります。
インハウスSEOに向けた移行プロセス

ここからは、外部委託からインハウスSEOへスムーズに移行するためのプロセスを解説していきます。
- ①SEOの基本と情報の集め方を学ぶ
- ②SEO分析と戦略立案に取り組む
- ③運用体制を設計して必要に応じて採用する
- ④SEO対策の実践と教育を行う
- ⑤②から④を繰り返す
内製化を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
①SEOの基本と情報の集め方を学ぶ
まずは、SEOの基本として、内部SEO、外部SEO、YMYL、E-E-A-Tなどの要素と検索エンジンの仕組みを学びましょう。書籍やオンラインセミナー、コミュニティなどを活用し、基礎知識を習得します。
また、最新情報を効率的に収集する方法も重要です。Googleが提供する「Google検索セントラルブログ」やコアアップデート情報を発信する「公式X」を始め、SEO情報を発信しているブログやXは積極的にチェックしておきましょう。
特に、Googleの順位変動を発信するXを日常的に確認することで、コアアップデートが発生した時にも冷静に対応できるようになります。
②SEO分析と戦略立案に取り組む
次に、Google Search ConsoleやGoogle Analyticsを用いて自社サイトの現状を把握します。検索キーワードやトラフィック状況から強み・弱みを分析し、改善の優先順位を決定します。
特に、検索順位の低いキーワードや、コンバージョン・トラフィックに繋がりやすいキーワードを特定し、その原因をコンテンツ内容や外部環境から分析します。
競合分析も重要です。SEOは絶対評価ではなく相対評価であるため、競合サイトのコンテンツや施策を分析しながら自社に不足している要素を把握することで、より効果的な施策を立案できるようになります。
③運用体制を設計して必要に応じて採用する
施策の立案後は、継続的な実施のための運用体制を構築する必要があります。コンテンツ作成には編集者やライター、デザイナー、技術的にはエンジニアが必要です。また、施策内容によっては営業や広報の協力も必要となるでしょう。
人員に加え、ツールの導入も検討します。すぐに最適なチームを編成できない場合もありますが、採用や教育を継続的に行い、段階的に運用体制を整えていきましょう。
④SEO対策の実践と教育を行う
戦略立案と体制の構築が完了したら、実際にSEO対策に取り組みます。キーワードに基づいたコンテンツ作成やリライト、クローラビリティ・サイトスピードの改善といった内部対策と、被リンクやサイテーションの獲得などの外部対策に取り組みましょう。
また、SEOに関する定期的な勉強会や研修を実施し、最新情報や成功事例を学ぶ機会を設けることも重要です。実践と教育を並行することで組織全体のSEOスキルが向上し、効果的な施策を継続的に実施できるようになります。
SEO対策は短期間で効果が現れるものではありません。施策を継続的に実行し、PDCAサイクルを回していくことで、徐々に成果が見えてきます。
⑤②から④を繰り返す
SEOは、継続的な改善が必要です。上記でご紹介した分析と戦略立案、運用体制の見直し、実践と教育を繰り返し、PDCAサイクルを回すことで、Webサイトの集客力向上と事業成長につながっていきます。
また、検索エンジンのアルゴリズムは頻繁にアップデートされるため、一度成功した施策でも時間が経つと効果が薄れてしまうことがあります。そのため、定期的なメンテナンスや情報の更新を行うことで、WebサイトのSEO効果を維持・向上させることができます。
常に最新の情報を収集し、自社の状況に合わせて施策を改善に取り組んでいきましょう。
インハウスSEOに必要なポジションやコスト

インハウスSEOを成功させるためには、適切な人材配置とコスト管理が重要です。特に必要なポジションは、以下のとおりです。
- 全体統括/マーケター
- 編集者
- ライター
- デザイナー
- エンジニア
全体を統括し戦略を策定するマーケター、コンテンツの品質を管理する編集者、文章を作成するライター、デザインを担当するデザイナー、そして技術的な対策に取り組むエンジニアなど、各ポジションが活躍することでSEOが円滑に進みます。
また、コンテンツ作成の実務を担うライターのコストは、SEO施策全体の費用に影響しますが、社内で制作する場合はコストを算出しにくい傾向にあります。
記事の費用は、一記事を制作するために発生した時間から計算しましょう。例えば、時間単価2,000円のライターが1記事あたり制作するために5時間かけた場合は、10,000円(2,000円×5時間)が記事の制作コストとなります。
特にプロジェクト発足当初は、費用計算の基礎データとして、一日あたりの制作記事数や一記事あたりの制作時間を記録しておくと良いでしょう。
インハウスSEOのありがちな失敗と対策

インハウスSEOの導入は、決して簡単な取り組みではありません。しかし、事前に多くの企業が経験する失敗を理解し、事前に対策を準備しておくことで、少ないリスクで内製化を進められるでしょう。
特にありがちな失敗とその対策をご紹介するので、インハウスSEOの構築と運用に役立ててください。
想定よりも工数と人員が必要になる
インハウスSEOでよくある失敗の一つは、想定よりも多くの工数と人員が必要になるという点です。
SEOは、キーワード選定やコンテンツ作成、技術的な最適化、効果測定と分析など、幅広い作業が必要です。また、コンテンツ作成一つをとってもライティングやデザイン、コーディングなど、様々なスキルが求められます。
このように、SEO施策全体を考えると複数の人員が必要になるため、想定よりも多くの工数と人員が必要となる場合があるのです。
そのため、各作業に必要なスキルや工数を見積もりつつ、必要に応じて部分的に外注することも検討していくことが大切です。
SEOの変化に追いつけずに流入が減り続ける
SEOは、検索エンジンのアルゴリズムアップデートなどにより、常に変化しています。そのため、情報収集を怠ると最新のSEOトレンドに追いつけず、結果としてWebサイトへの流入が減り続ける場合があります。
特に、コアアップデートは検索順位が大きく変動することがありますが、何が原因で順位が変動したのかを特定するのは難しい作業です。そして、適切な対策を講じることができずに、結果として順位が下がり続けるという状況に陥ってしまうのです。
Googleの基本方針である「Googleが掲げる10の事実」の理解を深めてコアアップデートがきても影響を受けにくいサイト制作を意識したり、外部のSEOセミナーや勉強会に参加したりしながら、最新の知識やトレンドを学ぶことが大切です。
短期的な成果を求めてリスクの高い取り組みを行う
短期的な成果を求めて、「ブラックハット」と呼ばれるリスクの高い取り組みを行ってしまうこともありがちな失敗の一つです。
コピーコンテンツの制作や被リンクの大量設置、隠しテキスト、隠しリンクなどは、一時的には効果を生む場合があります。しかし、いずれ検索エンジンからペナルティを受け、ウェブサイトの評価が大きく下落するリスクは小さくありません。
検索エンジンのガイドラインを十分に理解し、社内で共有すること、短期ではなく中長期的な視点でSEOに取り組むことが大切です。
インハウスSEOのよくある質問

SEOの内製化は多くのメリットがありますが、本当に成果が出るのか、自社は本当にインハウスSEOに適しているのかなど、疑問や不安に思うこともあるでしょう。
そこで、インハウスSEOに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q1.SEOの内製化に向かないケースはありますか
- Q2.SEOの内製化に必要な期間はどれくらいですか
- Q3.一部だけを内製化することは可能ですか
事前に疑問を解消し、安心して取り組めるようにしていきましょう。
Q1.SEOの内製化に向かないケースはありますか
SEOの内製化には、人的リソースや成果が出るまでの期間が必要です。そのため、SEOに割ける人員が不足していたり、ウェブサイトの運営規模が小さかったりする場合はSEOの内製化は難しいと言えるでしょう。
また、短期間で成果を出したい場合などは、外部の専門業者に委託する方が効率的かもしれません。Webサイトの規模や会社としての事業戦略などを総合的に考慮し、内製化が適切かどうかを判断することが重要です。
Q2.SEOの内製化に必要な期間はどれくらいですか
SEOの内製化に必要な期間は、企業の状況や目標によって大きく異なりますが、一般的には半年から1年以上かけて体制を構築していくケースが多いです。SEO担当者の知識獲得や実務の習熟、社内の理解などを、少しずつ浸透させていく必要があります。
特に内製化の初期段階では、担当者の負担も大きくなりがちです。それでも、インハウスSEOに取り組むことで、外部委託費用を削減できるだけでなく、自社ビジネスに合わせたSEO戦略を実行できるようになるでしょう。
長期的な視点で見れば、SEOの内製化は企業にとって大きな財産となると言えます。
Q3.一部だけを内製化することは可能ですか
SEOの一部のみを内製化することは十分に可能です。最も多いのは、ライティングは社外に依頼し、キーワード選定や分析を社内で行うケースです。特に、導入初期や社内での採用が難しい場合は、一部だけ内製化して徐々に内製化の範囲を広げていくとスムーズに業務を進められます。
部分的な内製化は、リソースの制約がある場合や専門知識を持つ人材がいない場合に有効です。自社の強みと弱みを分析し、効率的にSEOを進めていきましょう。
インハウスSEOを実現して運用効率を高めよう

インハウスSEOは、企業にとってノウハウの蓄積や迅速で柔軟な対応といったメリットが豊富にある一方で、体制の構築や運用には少なくない準備と継続的な取り組みが求められます。
インハウスSEOの導入は、決して簡単な取り組みではありません。しかし、長期的な視点で見れば、企業にとって大きなメリットをもたらす投資と言えるでしょう。
自社の状況をしっかりと分析し、適切な準備と継続的な取り組みを行うことで、インハウスSEOは必ず企業成長を促進してくれます。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
