
AIツール Jukeboxとは?使い方・料金プランや音楽生成の注意点を解説
Jukebox(ジュークボックス)は、高音質な楽曲を生成できる音楽生成AIとして注目を集めています。しかし、サービスサイトがないため、どのような手順で音楽を生成すれば良いのか、そもそもどのような特徴があるのかなど、よく分からないという方も少なくありません。
そこで本記事では、音楽生成AI JukeboxとはどのようなAIなのか、使い方や料金プラン、注意点について解説します。Jukeboxを活用して楽曲制作を楽しみたい、という方はぜひ参考にしてみてください。
目次
音楽生成AI Jukeboxとは
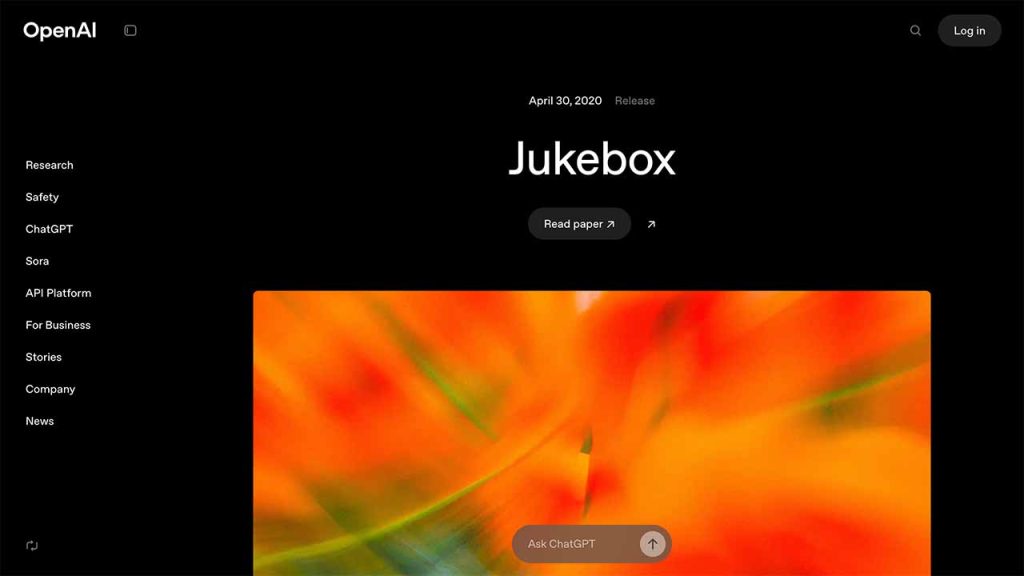
出典元:Jukebox
音楽生成AI「Jukebox」とは、OpenAIが開発した歌詞付きの楽曲を自動生成できるシステムです。音楽生成AIは近年急速に発展している分野で、多くの企業や研究機関が、AIによる音楽生成技術の研究開発を進めています。
Jukeboxには、オーディオデータの学習にニューラルネットワークが活用されています。ニューラルネットワークは人間の脳の神経回路の仕組みを模倣した計算モデルで、オーディオデータを分析し、リアルな楽曲を生み出すために活用されています。
また、オーディオデータを生成できる点もJukeboxの特徴です。多くの音楽生成AIはMIDIファイルで生成されるのに対し、JukeboxはオーディオデータであるWAV形式の音声ファイルとして保存します。
将来的には、Jukeboxの技術がさらに進化し、商業利用や楽曲制作のサポート、エンターテインメントでの活用が期待されます。
音楽生成AI Jukeboxの特徴

Jukeboxには、他の音楽生成AIとは一線を画す以下のような特徴があります。
- オーディオデータを生成できる
- 120万曲以上の楽曲を学習している
- 入力された歌詞に合わせて音楽を生成できる
より高音質で創造性の高い楽曲を生成できるのが大きな強みです。それぞれ、くわしく解説します。
オーディオデータを生成できる
音楽生成AI Jukeboxの特徴は、MIDIデータではなくWAV形式のオーディオデータを直接生成できる点です。オーディオデータとは音そのものをデジタル信号に変換したもので、CDや音楽配信サービスで耳にする音楽もオーディオデータとして保存されています。
従来の音楽生成AIは、MIDIデータと呼ばれる、音そのものではなく演奏情報を記録したデータを用いて音楽を生成していました。しかし、Jukeboxはオーディオデータを生成できるため、ギターの弦を擦る音やボーカルの息遣いのように、音楽の細かなニュアンスまで再現可能です。
Jukeboxで人間の演奏に近い楽曲を生成することで、新たな音楽や表現力の可能性が広がるでしょう。
120万曲以上の楽曲を学習している
120万曲以上の楽曲を学習していることもJukeboxの特徴です。学習データが多いほど、AIはジャンルごとの特徴やコード進行のパターンを正確に再現できます。
学習データは、AIにとって音楽の教科書のようなものです。AIは、多くの楽曲を学習しながら音楽の構造や法則を理解し、得た知識を応用して創造的な音楽を生み出します。
そのため、学習データがさらに増えるとAIが作る音楽の幅は広がります。過去の音楽スタイルと現代の音楽スタイルを融合させた新しい音楽を生み出したり、複数の音楽ジャンルを組み合わせた音楽を生み出したりできるようになるのです。
Jukeboxは、音楽生成AIの可能性を広げて行くでしょう。
入力された歌詞に合わせて音楽を生成できる
Jukeboxは、入力された歌詞に合わせた音楽生成も可能です。歌詞の内容を解析してメロディや伴奏を合わせられるため、より自然な楽曲を生み出せるのです。
従来の音楽生成AIは、歌詞とコード進行やメロディを独立して作成する手法が一般的でした。しかし、歌詞にはリズムやテンポがあるため、メロディと歌詞のリズムが合わなければ聴き手に違和感を与えやすくなります。そのため、作曲する際は歌詞の構造や音の響きを考慮しながらメロディを作る必要があります。
Jukeboxは、AIが歌詞のリズムを学習してメロディの構造を整えるため、違和感のない自然な楽曲の生成を実現しています。明るい歌詞には軽快なリズムを、落ち着いた内容には穏やかな伴奏を合わせられるのです。
Jukeboxを活用により制作の手間が軽減され、創作の幅が広がるでしょう。
Jukeboxの使い方の注意点
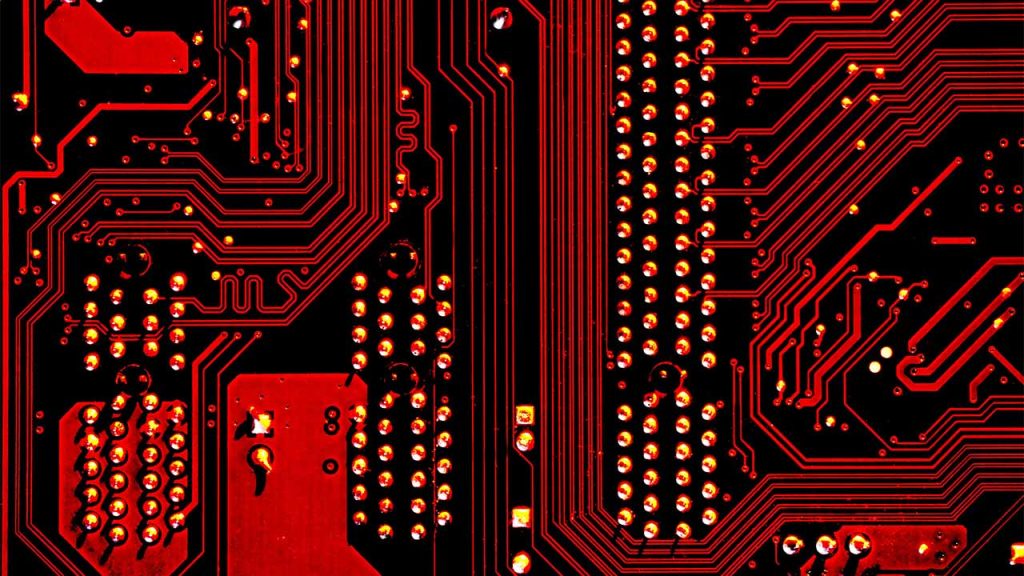
高音質な楽曲を生成できる反面、Jukeboxには以下のような注意点もあります。
- 一般向けのサービスサイトは用意されていない
- プログラミングの知識が必要
- 楽曲の生成に大量のリソースが必要
- 楽曲の生成は時間がかかる傾向にある
- 著作権の侵害に注意が必要
特に、実際に活用するためには専門の知識が求められる点には注意が必要です。それぞれ、解説します。
一般向けのサービスサイトは用意されていない
音楽生成AI Jukeboxは、一般向けのサービスサイトが用意されていない点に注意しなければいけません。
多くの音楽生成AIは、サービスサイトからジャンルや曲の雰囲気を選ぶだけで、楽曲を生成できます。しかし、Jukeboxにはサービスサイトがないため、利用するための環境を構築し、プログラミングを用いて楽曲を生成する必要があるのです。
また、Jukeboxによる音楽生成は高性能なGPUを用いた処理を前提としているため、Google Colab Proなどのクラウド環境を活用する必要があります。Jukebox自体は無料ですが、Google Colab Proを利用するためには有料プランの契約が求められる点にも注意が必要です。
Jukeboxにサービスサイトが用意されていない理由は、高度な計算リソースを必要とするため、サービスとしての提供が難しい点や著作権・倫理的な課題が考えられます。今後の動向に注目していきましょう。
プログラミングの知識が必要
Jukeboxで音楽を生成するためには、PythonやPyTorchなどのプログラミングの知識が必要な点も注意が必要です。そのため、知識や経験がない方には高いハードルとなるでしょう。
多くの場合、Jukeboxを利用する際はクラウド上でPythonを実行できるGoogle Colabを活用し、どのような曲調や歌詞にするかは全てプログラミング言語で記述する必要があります。
また、準備段階としてGoogle Driveと連携したり、Pythonライブラリをインストールしたりする際も全て記述が必要です。プログラミング初心者の場合は、まずは最低限の知識を身につけることから始めましょう。
楽曲の生成に大量のリソースが必要
Jukeboxを活用して楽曲を生成するためには、大量の計算リソースが求められることにも注意しましょう。一般的なPCでは処理が追いつかない場合もあるため、現実的には高性能なGPUを備えた環境やクラウドサービスの利用が求められます。
大量の計算リソースが必要になる理由は、JukeboxがVQ-VAE-2を活用した高度な生成モデルを採用し、数百万ものパラメータを処理しながら楽曲を構築しているためです。楽曲を一つ生成するだけでも、曲の長さによっては1時間以上かかるケースもあります。
大量のリソースは、クラウドサービスの利用により解決できます。ただし、無料プランでは難しく、有料プランでも時間はかかること、使用にはプログラミング言語の知識が求められることは理解しておきましょう。
楽曲の生成は時間がかかる傾向にある
Jukeboxを使った楽曲生成は、1曲あたりの処理時間が1時間以上かかる場合がある点にも注意が必要です。利用する際は高性能なGPUを備えたクラウド環境を用意することが前提となりますが、それでも処理時間が大幅に短縮されるわけではありません。
楽曲を作成したい場合は、長時間の処理を想定した運用が求められます。楽曲生成に時間を取れない方や、すぐに曲を制作したい方には不向きと言えるでしょう。
音楽生成AIは、まだまだ研究途中の技術です。将来的には、機械学習技術やハードウェアの進化により、処理時間の短縮が期待されています。しかし、現時点では十分な時間を確保した上での利用が必要です。
著作権の侵害に注意が必要
Jukeboxを使用する際は、著作権の侵害にも注意しなければいけません。特に商用目的で利用する際は、著作権者の権利を侵害しないよう慎重な確認が必要です。
Jukeboxは、既存の楽曲データを学習して音楽を生成します。そのため、生成された楽曲が既存の作品と非常に似ている場合、著作権法に違反する可能性があるのです。
Jukeboxに限らず、生成AIによるコンテンツの著作権問題は、今後も議論が続く分野です。音楽生成AIの技術は進化していますが、著作権に関するルールやガイドラインはまだ発展途上にあります。
安全に活用するためには、現行の著作権法を理解し、適切な運用を心がけることが大切です。
Jukeboxの料金プラン

Jukeboxは、基本的に無料で利用できる音楽生成AIです。ただし、本格的に活用するにはGoogle ColabのColab Pro以上のプランが推奨されます。
Google Colabの無料プランでも試せますが、使用時間やリソースの制限があります。Google Colabの料金プランは以下の通りです。
| プラン名 | Colab Pro | Colab Pro+ |
| 月額料金 | 1,179円 |
5,767円 |
| ユニット数 | 100コンピューティング ユニット |
400コンピューティング ユニット |
| メモリ容量 | 最大32GB |
最大52GB |
| GPU | 強力なGPUにアップグレード |
強力なGPUを優先的に利用可能 |
出典元:Colab 有料サービスの料金
特に重要なのが、画像や映像の処理を行うGPU(Graphics Processing Unit)と呼ばれるプロセッサです。無料版は性能の低いNVIDIA T4が割り当てられますが、Colab ProやColab Pro+には、より高規格のNVIDIA Tesla P100やVNVIDIA Tesla A100が割り当てられます。
また、ユニット数とは計算リソースの利用量で、数値が高いほど高性能なGPUや長時間のセッションを利用できます。実際の利用状況に合わせて、プランを選択していきましょう。
Jukeboxの使い方

ここからはJukeboxの使い方について解説します。手順は以下の通りです。
- Google Colabをセットアップする
- Googleドライブをマウントする
- モデルを選択する
- プロンプトを入力する
- 楽曲の生成を開始する
- 生成した楽曲を保存する
- パラメータを調整して生成結果を変える
なお、実際のソースコードについてはGitHubなども参考にしてみてください。
Google Colabをセットアップする
まず、Googleが提供するGoogle Colabをセットアップします。Googleアカウントを準備し、Google Colabのトップページにアクセスしましょう。
Colabのページが開いたら、「新しいノートブック」を作成します。画面上部の「ランタイム」メニューを開き、「ランタイムのタイプを変更」を選択、「ハードウェアアクセラレータ」の項目で任意のGPUを選び、保存を押しましょう。
続いて、Jukeboxを動作させるために、必要なパッケージとライブラリをインストールします。Colabのaコードセルにコマンドを入力し、実行しましょう。なお、インストールには数分かかることがあります。
Googleドライブをマウントする
次に、Google ColabからGoogleドライブのファイルやフォルダに直接アクセスできるようにマウントします。
コードを実行すると、Googleアカウントの認証が求められます。指示に従って認証を完了させると、作業ディレクトリがGoogleドライブ内のMyDriveフォルダに移動します。
この作業により、楽曲データをGoogleドライブに保存したり、Googleドライブ内の音楽ファイルをColabで処理したりできるようになります。
モデルを選択する
Jukeboxには複数のモデルが用意されており、生成する楽曲の品質や処理時間が異なります。
主なモデルとして「5b_lyrics」「5b」「1b_lyrics」があり、最も軽量な「1b_lyrics」は処理が速いですが、音質が劣る場合があります。一方、「5b_lyrics」は高品質な楽曲を生成できますが、より多くのリソースと時間を必要とします。
プロンプトを入力する
実際に、どのような楽曲を生成するのか、アーティスト名、ジャンル、歌詞などのプロンプトを設定します。プロンプトを入力することで、Jukeboxは指定されたスタイルや内容に沿った楽曲を生成します。
楽曲の生成を開始する
設定が完了したら、楽曲の生成を開始します。プロンプトとは別に生成用のコードが必要になるため、入力して実行しましょう。
生成した楽曲を保存する
生成が完了した楽曲は、Googleドライブに保存しておくと便利です。生成されたwavファイルをドライブ内の指定したフォルダに保存することで、後で再生したり、共有したりなどの手間を軽減できます。
パラメータを調整して生成結果を変える
Jukeboxでは、温度(temperature)や反復回数(iterations)、サンプル数などのパラメータを調整することで、生成される楽曲の特性を変えられます。温度を変更すればよりランダム性の高い結果が得られるため、様々なバリエーションの楽曲を生成できます。
パラメータを試行錯誤しながら調整し、理想的な楽曲を生成しましょう。
Jukeboxを活用して高音質の音楽を生成しよう
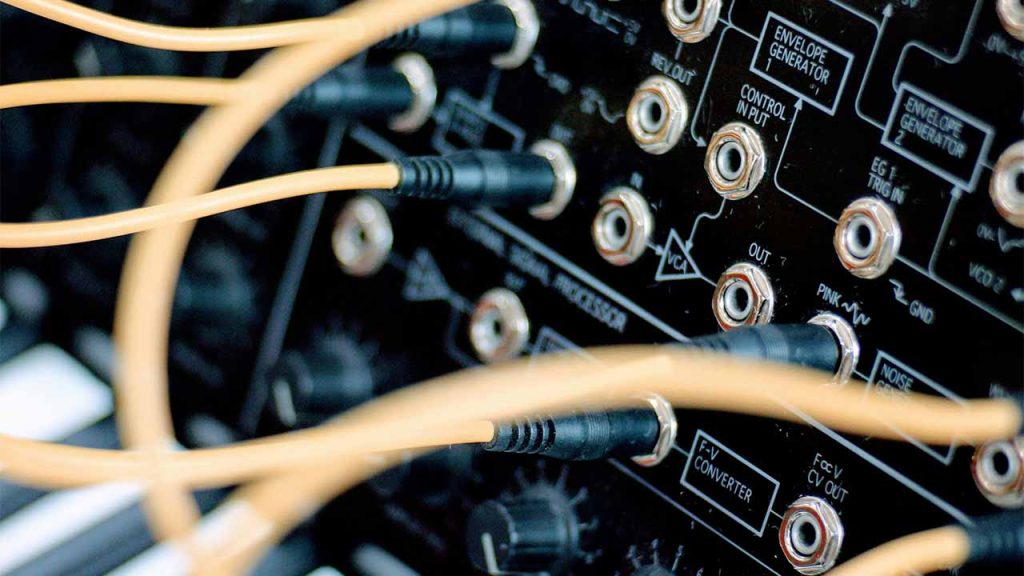
Jukeboxは、OpenAI社が開発している音楽生成AIです。オーディオデータを生成できる点が他の音楽生成AIとは異なる特徴で、より高音質で自然な楽曲を生み出せます。
研究を目的としているため、一般向けのサービスサイトは用意されていませんが、プログラミングの知識や環境を整えられれば、個人でも楽曲生成が楽しめます。
著作権や楽曲生成に時間がかかるなどの注意点を事前に理解した上で、紹介した使い方の手順に沿って高音質の楽曲制作を楽しみましょう。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
